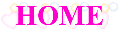| 他県・世界の動き | 山口県の動き |
|
2000.05.28. NHKの番組で米国CRT紹介 |
1991.02. 第1回フォーラム 1996.02.03. アディクション研究会発足 |
|
2001.02.10. えひめ丸事故 2001.06.08. 大阪教育大付属池田小事件 2001.08. 福岡県臨床心理士会が手引き発行 |
2001.04.01. 協会にア研究会合流 2001.06.09. 池田小事件翌日に山口県CRT準備開始 |
|
2002.03.11〜13. PTSD対策専門研修会(厚労省) 2002.03. トラウマティックストレス学会発足 |
2002.08.31〜09.01. 第1回ハートワープ研修会 |
|
2003.07.02. 長崎市4歳男児誘拐殺害事件 2003.12.18. 京都宇治小侵入事件 |
2003.03.17. 情報センター立ち上げ 2003.05. 山口県CRT出動可能に 2003.08.23〜24. 第2回ハートワープ研修会 2003.08.23. 山口県CRT正式スタート 2003.10.19〜21. 第1回出動 2003.12.10〜12. 第2回出動 |
|
CRT 「こころのレスキュー隊」とも言うべきCRTの存在を知ったのは、 2000年5月28日に放映されたNHK番組「世紀を超えて いのち 生老病死の未来 第4集 トラウマ・こころの傷」でした。 日本にもこんなチームがあったらいいなとは思いましたが、 学校で銃撃事件が起こるアメリカならではで、 まさか翌年自分たちが取り組むことになろうとは夢にも思いませんでした。 大阪池田小事件(2001年6月) 全ての始まりは2001年6月の大阪池田小事件からでした。 「通学路は危険であっても、学校に行っている間は大丈夫」という神話が崩壊した日です。 もはや学校は安全な場所ではないことが突きつけられました。 「もしわが子の通っている学校でこのような事件が発生した時の心のケア態勢はどうなのか」と 見回してみると、当時はとてもお寒い限りの状況でした。 起こってからあわてるよりも、今から準備しておこうと考え、 心の専門家による危機対応チーム(CRT)を作ろうと考えたわけです。 たまたま事件翌日に山口県精神保健福祉協会の運営委員会(写真)が開催され、 この会議の席で、専門家による対応チーム作りを 緊急提言 し、同志を募り、準備を始めました。 |

|
児童虐待・暴力防止専門部会(2001年7月) 児童虐待・暴力防止専門部会の第8回定例会(写真)でCRT(仮称)について協議しました(7/30)。 専門会員の中から、この分野の専門家を今後チームメンバーとして登録していき、 研修を行う予定であることや、即応できる体制づくりなどを説明しました。 この段階で、「指揮担当、直接ケア、補助業務」という基本骨格はできていました。 課題は、学校や教育委員会から呼んでいただけるかどうかと、 中長期のアフターケアをどうするかでした。 打開策が見いだせないまま半年が経ちました。 |

|
PTSD対策専門研修会と学会(2002年3月) H13年度から厚労省のPTSD対策専門研修会(こころの健康づくり対策研修会)が始まりました。 また、「PTSDの学会」である、日本トラウマティック・ストレス学会(JSTSS)が発足しました。 大阪池田小事件のみならず、奥尻島、ガルーダ機事故、桑名ヘリ空中衝突事故、和歌山毒物カレー事件、 などなど、様々な災害・事件への支援について報告を聞く機会がありました。 アフターケアをどうするかを考えあぐねていましたが、 「CRTは緊急対応だけでアフターケアはしない」と割り切ることができました。 この学会で、聖マリアンナ医学研究所カウンセリング部の藤森和美さんに研修会の講師をお願いしました。 第1回ハートワープ研修会(2002年8月) 動ける専門家の確保、研修と、教育関係者との風通しを良くする必要があることから、 専門職と教育関係者が一緒に学べるような研修の場として、 8月31日(土)〜9月1日(日)にハートワープ研修会を開催しました。 ハートワープは、困った時にはハートがワープして助けに来てくれるという意味の CRTの愛称です(実際には使われませんでしたが…)。 約60名の参加があり、職種で多かったのは、心理、保健師、PSW。 教育委員会から4名、他教員が10名弱。警察2、精神保健行政2。他は看護職、精神科医等々。 全体の6割は公務員でした。 この日からCRT仮登録を始めました。 マスコミは、新聞3社、テレビ1社が報じました。 2003年4月スタートが報道されましたので、もう後には引けなくなりました。 学校などからの出動要請を受ける「情報センター」を防府海北園にお願いしました。 |
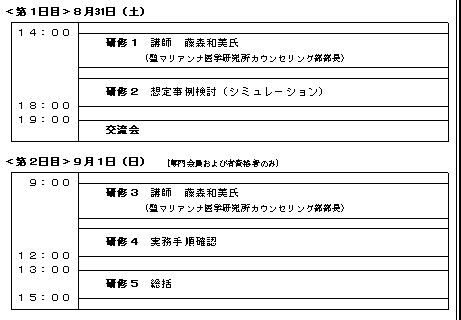
|
1日目は、どちらかと言うと学校向けのお話。まず研修1は藤森さんの講演(写真)。
研修2では、小学校のすぐ近くに給油機が墜落したとの想定で、
5グループに分かれて、対応方法など協議しました(写真)。模擬記者会見もしました。
現職の記者や教育委員会職員が校長役で汗をかきながら会見したり、返答に窮すると教頭に丸投げしたり、
まわりを威圧して質問を許さなかった強者がいたりいろいろでした。 2日目は、CRT参加を考えている人向けの研修でした。研修3は藤森さんの講演。 研修4はCRT河野委員長から実務手順の説明と意見交換。 研修5(午後)は、まず阪神大震災支援者の体験談に始まり、 最後まで残った約30数名全員が感想を述べました。 何か起これば自分も現地に行くかもしれないという緊張感に満ちていて、 全体として「濃い」研修会でした。 |


|
ハートフォーラム(2003年2月) 専門会員にとって年に一度のフォーラムです。 再度藤森さんにお越しいただきました。春にはスタートする予定であることなど確認しました。 フォーラム終了後、仮登録者は約30人となりました。 |


|
情報センターの立ち上げ(2003年3月) 懸案であった情報センターの講習会を児童養護施設海北園で開きました。 実際に出動要請の電話があって、どう連絡を入れていくかの手順(出動シークエンス)の確認を行いました。 この後、先行して10人を正式登録し、CRTは5月には出動可能となりました。 |

|
県・県教委との調整(2003年5月〜7月) 行政(県や県教委)といろいろな調整をしました。 偶然ですが、CRT河野委員長は2003年5月に大学病院から精神保健福祉センター所長に就任し、 廣岡副委員長は4月に児童相談所からセンターに異動となりました。 |
| 正式スタート 第2回ハートワープ研修会(2003年8月23日) 正式スタートが4カ月遅れましたが、第2回研修会において正式スタートしました。 会長挨拶はこちら |
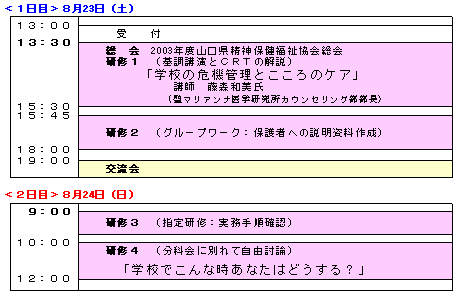


|
えっ?こんなはずでは! CRTは8月に正式スタートし、新聞報道もされました。 「いきなり大きな事件が起きませんように」というのが、隊員の率直な願いでした。 逆に、ひょっとして2〜3年何も起こらないと、 CRTの存在が忘れられるのではという危惧も抱きました。 しかし、それは杞憂に終わりました。 10月に第1回出動、12月に第2回出動と続いたのです。 隊員の中には訓練通報かと勘違いした人もいました。 |
|
第1回出動 2003年10月19日(日)〜21日(火) 衝撃度III弱 山口市で小6の双子が母親に絞殺され、母親は自殺を図りました(未遂)。 公立小学校の依頼で同小学校へ6人(延べ15人)の隊員を派遣しました(6人全員初出動)。 詳細はこちら。 ●1日目6人、2日目5人、3日目4人。 ●医師2人、臨床心理士2人、精神保健福祉士1人、その他1人。 ※CRTに登録されている精神保健福祉センター職員2名は、業務の一環として参加し、 県としても直接関与することになりました。 アフターケアのために精神保健福祉センターが職員を2回派遣しましたが、 すぐに次の出動があり、以後は行わないこととしました。 |
|
第2回出動 2003年12月10日(水)〜12(金) 衝撃度III弱 小学3年の男児が母親に絞殺され、中学2年の兄が負傷、母親は自殺しました。 市教育委員会の依頼で公立小学校に7人(延べ15人)の隊員を派遣しました(初出動2人)。 詳細はこちら。 ●1日目7人、2日目5人、3日目3人。 ●医師2人、臨床心理士1人、精神保健福祉士1人、看護師1人、その他2人。 |




|
始めて出動した隊員の感想(抜粋) ●初回の出動は、とにかく慌てました。出発前に洗濯をしようとしたり、 普段では考えられない行動をしている自分に気づきました。 ●初めての出動でとても緊張し、最初のあの緊迫感に圧倒されておたおた、もたもたしている自分がおりました。 ●CRT情報センターからの電話はいつも突然です。次回も「訓練ですか?」と聞きそうです。 ●CRT初めての体験のため、緊張と不安の連続でしたが、皆さんの暖かさに助けらなんとか終える事が出来ました。 私には耐えがたいことばかりでしたが、今回の経験はこれからの自分に大きな影響になることは間違いないと思います。 |